 悩んでいる人
悩んでいる人子どもが離乳食を食べないから疲れてしまいました。どうすればいいでしょうか。
こんな悩みに答えます!
- 子どもが離乳食を食べなくて疲れてしまった時の対処法
赤ちゃんが離乳食を食べないと、「どうして食べてくれないの?」と悩んだり、疲れ果ててしまうこと、ありますよね。
周りの子がモリモリ食べている様子を見たりすると、余計に不安になってしまうことも。
でも、大丈夫です!赤ちゃんにはそれぞれのペースがあり、少しずつ慣れていくものです。
この記事では、赤ちゃんが離乳食を食べないときに役立つ具体的な対処法をたっぷりご紹介します。
「これなら試せるかも!」と思えるヒントが見つかるはずなので、ぜひ気楽な気持ちで読んでみてくださいね。
親も赤ちゃんも、無理せず、楽しく食事の時間を過ごせるよう、一緒に考えていきましょう!
Amazonの公式サービス「らくらくベビー」に登録すれば、お買い物金額合計10万円まで、最大10%引きでベビー用品を買えるようになります!
つまり最大1万円の割引に!1万円分のクーポンがもらえるのと同じですね。
しかも、登録は無料!使わないのはもったいないです!



登録方法は、赤ちゃんの誕生日か出産予定日を入れるだけです!3分くらいでできるので、忘れずに登録しておきましょう。
\ ずっーと無料/
出産前でも出産後でも登録OK!
子どもが離乳食を食べなくて疲れた時の対処法26選



子どもが離乳食を食べなくて疲れてしまった時の対処法を教えてください。
子どもが離乳食を食べなくて、疲れ切ってしまう時もありますよね。
そんな時は以下のことを試してみるといいでしょう!
- 無理しない!ママもパパも休憩を大切に
- 食事を遊びの一環にしてみる
- 食材の味付けや硬さを見直す
- 赤ちゃんの体調をチェック
- 一緒に食卓を囲む
- 時間帯を変えてみる
- 食事の量を調整する
- 好きな食材を活かす
- 気分転換に外食風の環境を作る
- おやつ感覚で食べさせてみる
- 周りの人に相談する
- 手抜きしてOK!ベビーフードも活用
- 焦らず、赤ちゃんのペースを信じる
- 食材の色や形を変えてみる
- 味見させながら作る
- 食器を変えてみる
- ルールを柔軟にする
- 家族以外の人に食べさせてもらう
- 食べないことも「個性」と捉える
- 家族の声かけをポジティブにする
- ストーリーを作って食べさせる
- 食材を手に取らせる時間を増やす
- 食べられるものをストックしておく
- スマホやおもちゃを使う場合は計画的に
- パートナーと役割分担をする
- 食べないことに一喜一憂しない
それぞれ解説していきます。
無理しない!ママもパパも休憩を大切に
赤ちゃんが離乳食を食べないと、つい焦ったりイライラしたりしがちですが、まずは自分を責めないでください。
赤ちゃんにもペースがあるので、無理強いすると逆効果になることもあります。
「今日はダメだったな」と思ったら、思い切ってお休みしてみるのも一つの方法です。
赤ちゃんの食事は長い目で見て、少しずつ進めていけば大丈夫です。
親が笑顔でいることが、一番の離乳食サポートです!
食事を遊びの一環にしてみる
赤ちゃんにとって、食べることは新しい体験そのもの。
スプーンを持たせてみたり、手で触らせてみたりして、食材や食器に慣れさせる時間を作ると良いですよ。
食べることへの興味を持つきっかけになることがあります。
汚れるのを気にせず、「自由に触ってOK!」と割り切ると、ママパパのストレスも減ります。
食材の味付けや硬さを見直す
赤ちゃんが食べない原因の一つに、「味が苦手」「硬さが合わない」という可能性があります。
甘みが少ない場合は、野菜の自然な甘みを活かして調理してみましょう。
また、硬さが気になる場合は、柔らかく煮たり、ペースト状にして再挑戦してみてください。
赤ちゃんの好みを探る時間だと思って、いろいろ試してみるのがポイントです。
赤ちゃんの体調をチェック
実は、体調が良くないときに食べないことも多いです。
風邪気味やお腹の調子が悪いときは、離乳食を嫌がることがあります。
食べなくても気にせず、機嫌や健康状態を優先してください。
体調が整えば、また食べてくれるようになります。
一緒に食卓を囲む
赤ちゃんは周りの人の行動を真似するのが大好きです。
家族みんなで同じ時間に食卓を囲むことで、「食べるって楽しいことなんだ」と感じてもらうことができます。
大人が美味しそうに食べている姿を見せるだけで、赤ちゃんの興味を引きやすくなりますよ。
時間帯を変えてみる
赤ちゃんが疲れている時間帯だと、食べる意欲が湧かないこともあります。
タイミングを見直して、機嫌が良いときにチャレンジするのも有効です。
たとえば、朝早すぎる時間帯やお昼寝直前などは避けてみましょう。
リラックスできる時間に合わせてみてください。
食事の量を調整する
大人と同じ感覚で量を考えると、赤ちゃんにとっては多すぎる場合があります。
少量から始めて、食べられる範囲でストップすることを心がけてみてください。
無理に量を増やさなくても、徐々に慣れていけば十分です。



毎回作っていると時間も手間もとられるから、ベビーフードも使っていこう!
好きな食材を活かす
赤ちゃんが好きな食材が見つかったら、それを活かしてメニューを工夫してみましょう。
例えば、かぼちゃが好きなら、かぼちゃを使ったスープやおやきにアレンジしてみると、食べる意欲がアップすることがあります。
好きなものを基準に、少しずつ新しい食材にチャレンジしてみるのもコツです。
気分転換に外食風の環境を作る
普段と違う雰囲気で食べると、赤ちゃんも気分が変わることがあります。
例えば、ピクニック気分でリビングでレジャーシートを敷いて食べるなど、特別感を演出してみてください。
赤ちゃんがワクワクするような工夫が、新しい刺激になることもあります。
おやつ感覚で食べさせてみる
どうしてもご飯の時間がうまくいかない場合は、おやつタイムを活用してみるのも一つの手です。
お腹が空いているタイミングなら、食べやすいスティック状のものやおかゆを少しずつ与えてみてください。
食べることに慣れてくれれば、それが一歩前進です。
周りの人に相談する
育児は一人で抱え込まないことが大切です。
地域の保健師さんや育児サークルに相談することで、具体的なアドバイスをもらえることがあります。
他のママたちの経験を聞くと、「うちだけじゃないんだ」と気持ちが楽になりますよ。
手抜きしてOK!ベビーフードも活用
疲れてしまったときは、市販のベビーフードを賢く活用するのも大事です。
プロが栄養バランスを考えた商品なので、安心して使えます。
「自分で作らないと…」とプレッシャーを感じず、頼れるものには頼りましょう。
焦らず、赤ちゃんのペースを信じる
最後に一番大事なのは、赤ちゃんのペースを尊重することです。
食べない時期は必ず終わるので、焦らなくても大丈夫です。
親も赤ちゃんも初めての経験。
少しずつ一緒に成長していけると思えば、心も軽くなりますよ。
あなたも赤ちゃんも、ちゃんと頑張っています。
大丈夫、少しずつ前に進んでいますよ!
食材の色や形を変えてみる
赤ちゃんは見た目でも食べ物に興味を持ちます。
カラフルな野菜や、星形やハート形に切った食材を使うことで、視覚的に楽しんでもらうことができます。
例えば、にんじんを薄切りにしてクッキー型で抜いたり、パンケーキを小さな丸形で焼いたりするのもおすすめです。
「食べてみたい!」と思わせる工夫が大切です。
味見させながら作る
赤ちゃんも、作る過程に参加すると興味を持つことがあります。
安全な範囲で、調理中にスプーンで味見させると、「なんだろう?」と興味を持つかもしれません。
簡単なものなら、例えばヨーグルトにフルーツを混ぜる作業を一緒にしてみるのも楽しいですね。
食器を変えてみる
お気に入りのキャラクターが描かれた食器や、明るい色のお皿に変えるだけで、食卓が楽しい雰囲気になります。
また、赤ちゃん専用のスプーンやフォークを持たせてあげると、「自分でやってみたい」という気持ちが湧くことがあります。
食器一つで気分が変わることもあるので、ぜひ試してみてください。
ルールを柔軟にする
「絶対に椅子に座って食べなきゃダメ!」と決めてしまうと、お互いにストレスになる場合があります。
時には膝に抱っこしたり、場所を変えて気分を変えてみることも効果的です。
リラックスできる環境で食事を進めることを優先してみましょう。
家族以外の人に食べさせてもらう
赤ちゃんは時々、家族以外の人に食べさせてもらうと、新鮮さを感じて意外と食べてくれることがあります。
おじいちゃんやおばあちゃん、親しい友人などにお願いしてみてください。
違う雰囲気や声掛けが良い刺激になることがありますよ。
食べないことも「個性」と捉える
赤ちゃんの性格や好みによって、食べるスピードはそれぞれ違います。
たくさん食べる子もいれば、少食の子もいます。
「この子の個性なんだな」と前向きに考えることで、気持ちが軽くなることもあります。
長い目で見て、その子に合った方法を探していきましょう。
家族の声かけをポジティブにする
赤ちゃんは大人の言葉や態度に敏感です。
「また食べないの?」ではなく、「ちょっとでも食べられてすごいね!」とポジティブな言葉をかけてあげることが大事です。
その一言が、赤ちゃんのやる気につながります。
ストーリーを作って食べさせる
赤ちゃんにとって楽しいストーリーがあると、食事がもっと面白くなります。
例えば、スプーンを電車に見立てて、「ご飯が電車でお口に向かっています!到着〜!」と遊び感覚で食べさせると笑顔になることがあります。
食べることを特別な体験にしてみましょう。
食材を手に取らせる時間を増やす
赤ちゃんにとって「触ること」も食事の一部です。
手で野菜を握ったり、スプーンをカチャカチャしたりするだけでも、食事への興味を深めるきっかけになります。
多少汚れてもOKと思えるように、防水シートやお手拭きを準備しておくと安心です。
食べられるものをストックしておく
赤ちゃんが気に入っている食材やメニューが見つかったら、いつでも食べられるようにストックしておくと便利です。
例えば、冷凍できるおかゆやスープを小分けにして保存したり、市販のベビーフードを買い置きしておくと、「食べてくれない!」と焦る場面を減らせます。
スマホやおもちゃを使う場合は計画的に
「スマホやおもちゃで気を引いている間に食べさせる」という方法も時には有効ですが、依存しすぎないよう注意が必要です。
どうしても食べてくれないときの最終手段として使い、少しずつ減らしていく方向で進めると良いでしょう。
パートナーと役割分担をする
離乳食の悩みを一人で抱え込む必要はありません。
パートナーと役割分担を決めることで、負担を軽減することができます。
例えば、調理はママが担当して、食べさせるのはパパが担当するなど、得意分野を活かす形で進めるとスムーズです。
食べないことに一喜一憂しない
最後に、食べない日が続いてもあまり心配しすぎないことが大切です。
赤ちゃんの成長は少しずつ。
離乳食は、食べ物を口にする練習期間と捉えれば、プレッシャーも軽くなります。
焦らずゆったりした気持ちで向き合ってくださいね。
まとめ「子どもが離乳食を食べなくて疲れた時は無理しないで」
赤ちゃんが離乳食を食べないときは、どうしても焦りや不安がつきまといますが、大事なのは長い目で見ることです。
どんな子でも、いずれは食べられるようになりますし、食べる楽しさを感じられる日が必ずやってきます。
親が疲れすぎず、笑顔でいられることが、赤ちゃんの成長には何よりも大切です。
この記事の対処法を参考にして、ぜひ無理のない範囲でいろいろ試してみてください。

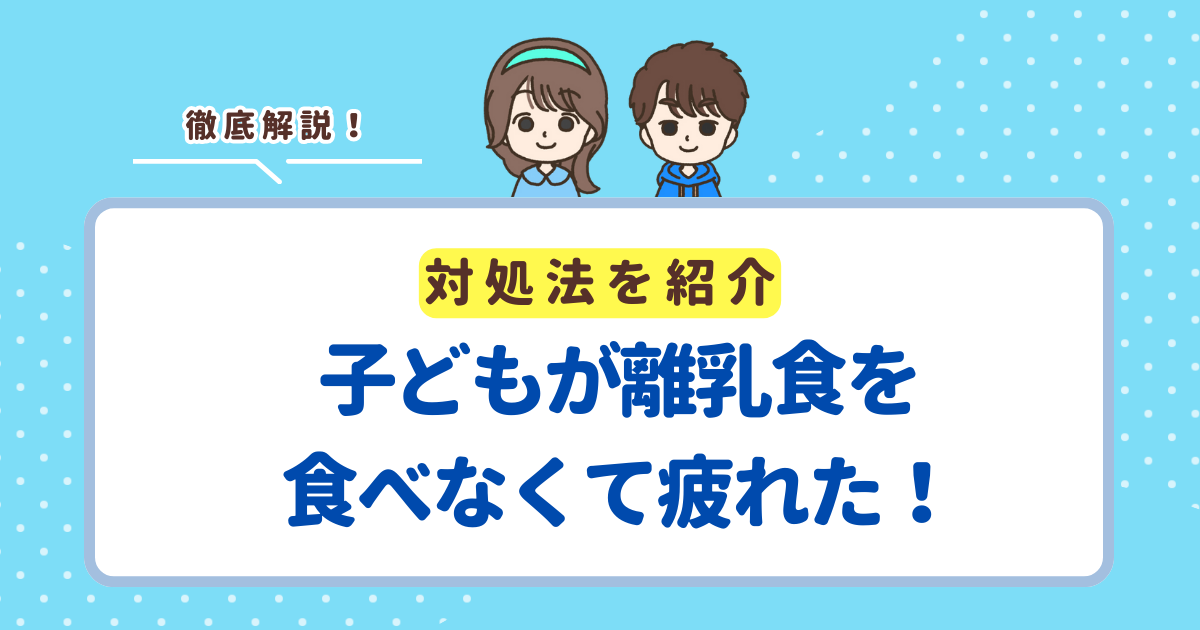
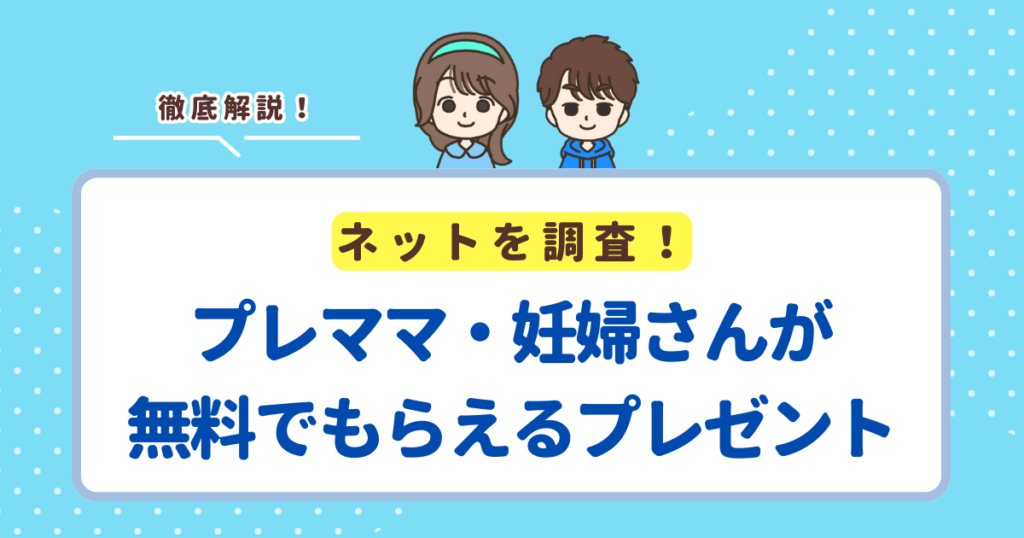
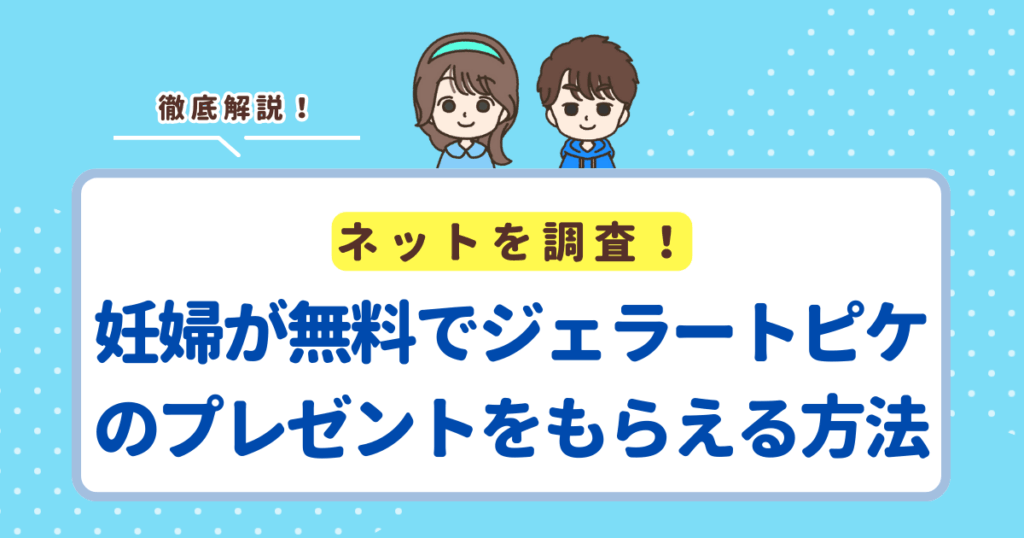
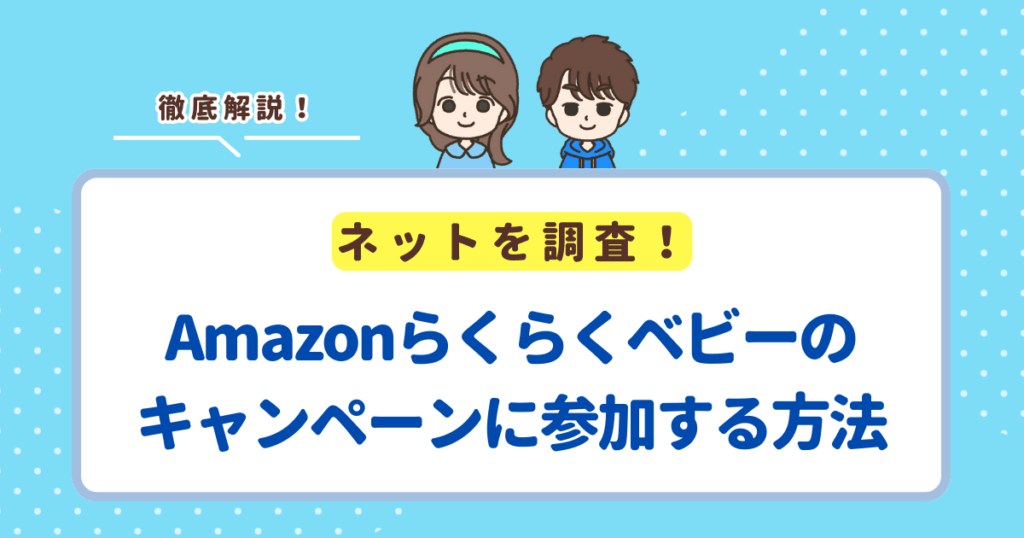
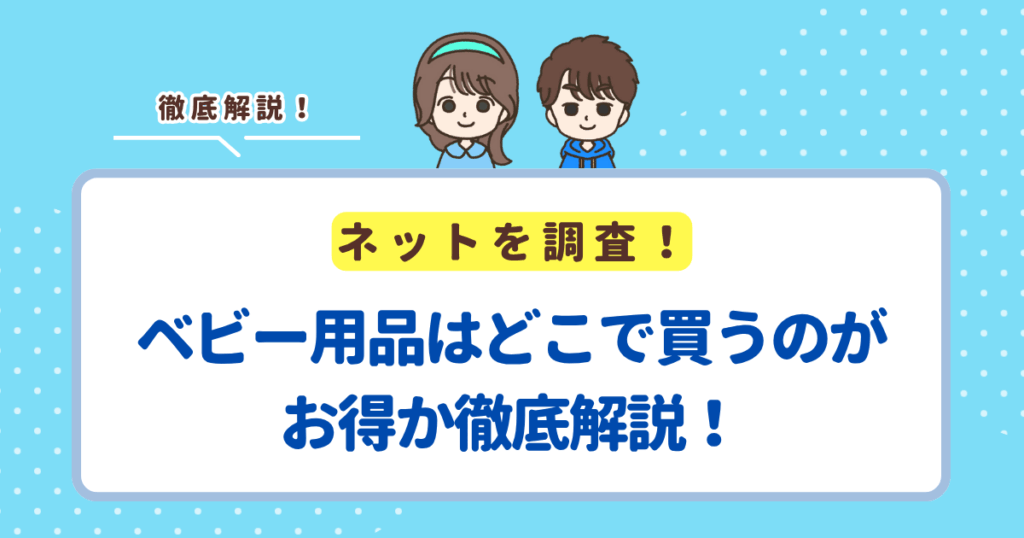

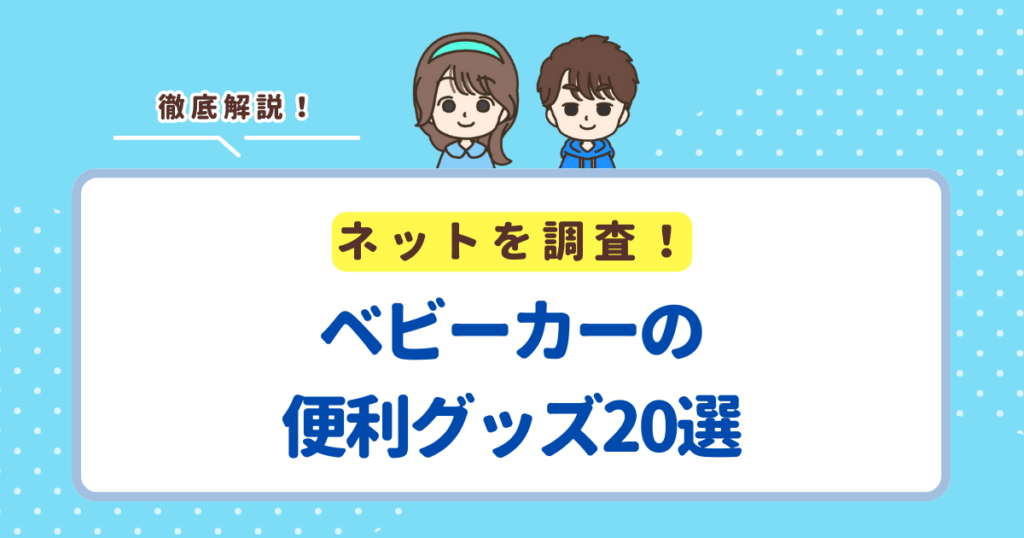
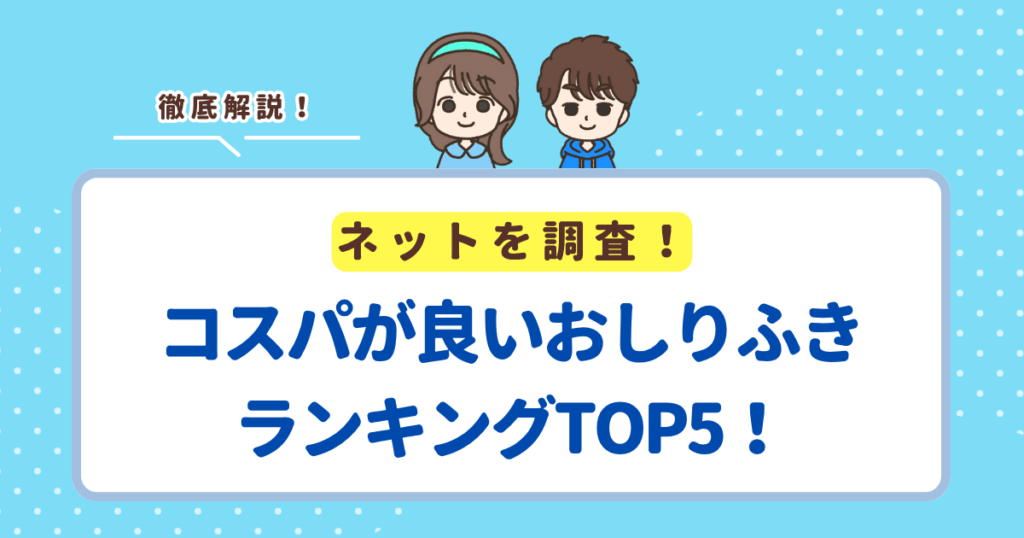
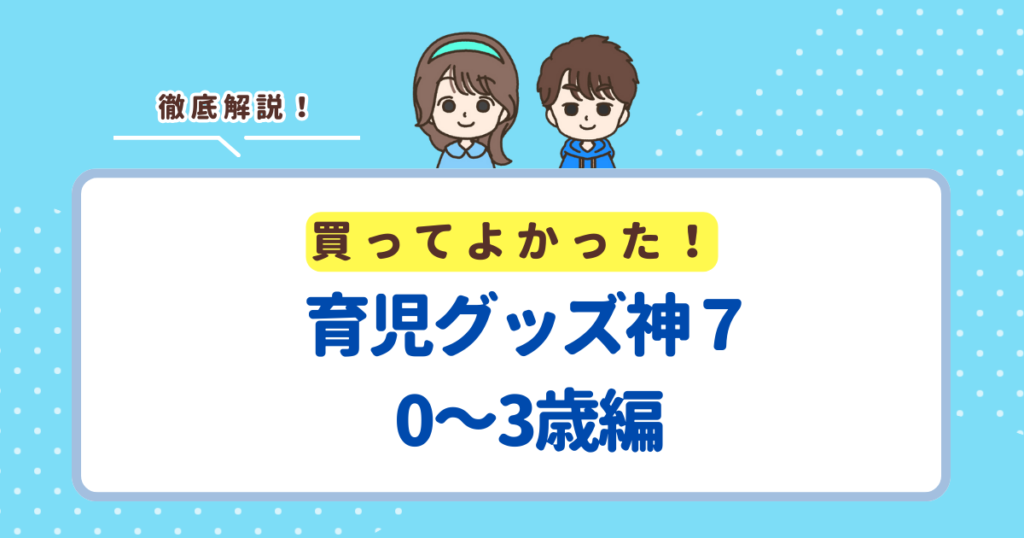
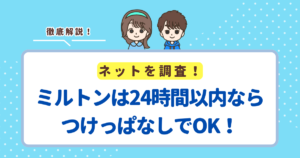
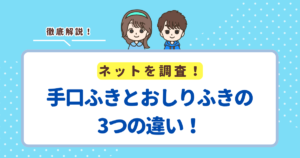
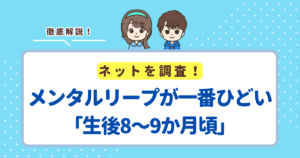
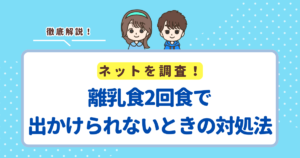
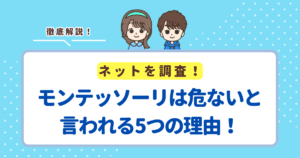
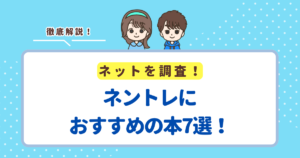

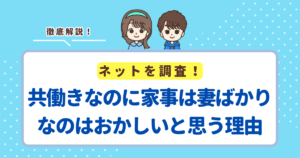
コメント