今どきの子どもの習い事、びっくりするくらい進化してるんです。
昭和の時代といえば、「ピアノ・そろばん・習字」が王道でしたよね。
どれも「静かに座ってコツコツ練習」というイメージがあって、ちょっと堅苦しい印象もあったかもしれません。
でも、令和の子どもたちが夢中になっている習い事は、まったく別モノです。
ゲーム感覚で学べるものや、身体をめいっぱい使うアクティブ系、さらにはSNS映えまで意識された習い事まで登場しています。
「えっ、こんなのも習い事になるの?」と驚くようなラインナップばかり。
今回は、そんな令和のキッズに人気のちょっと変わった習い事を10個ご紹介します。
親世代の「習い事感覚」との違いを楽しみながら、未来の選択肢として参考にしてみてくださいね。
子どもに習わせてよかった習い事ランキングTOP10
それでは、今どきの子どもたちがハマっている最新の習い事ランキングTOP10を発表します。
どれも一度聞いたら気になってしまう、ユニークで魅力的な内容ばかりですよ!
第1位:マイクラの習い事(プログラミング×創造力)

今や「遊び」と「学び」が見事に融合しているのが、マインクラフトを使ったプログラミング教室です。
「ただのゲームじゃないの?」と思いきや、これがすごいです。
論理的思考や創造力、空間認識能力などが自然と身につくと話題なんです。
「将来はゲームクリエイターになりたい」という子にもぴったり。
好奇心を学びに変えるきっかけになる、まさに令和の習い事代表格です。
| 対象年齢 | 料金目安 |
|---|---|
| 小1〜中学生 | 月8,000〜12,000円 |
マイクラを習うメリット
マイクラを使った学習の一番のメリットは、遊びながら論理的思考が自然と身につくところです。
子どもたちは自分で世界を作り上げていく中で、「どうしたらうまく動くか」「どんな仕組みにしようか」と試行錯誤します。
また、空間認識能力や発想力が鍛えられるので、創造的な職業に興味があるお子さんには特におすすめです。
第2位:ボルダリング(身体能力×思考力)

壁を登るスポーツ「ボルダリング」も、今注目の習い事のひとつです。
一見シンプルですが、実はどうやって登るかを考える思考力と、全身のバランス感覚が鍛えられる優秀な運動なんです。
特に「球技が苦手」「体育が嫌い」という子にも人気があって、自分のペースでチャレンジできるのが魅力です。
| 対象年齢 | 料金目安 |
|---|---|
| 5歳〜 | 1回2,000円前後/月謝制あり |
ボルダリングを習うメリット
ボルダリングはただの運動ではなく、「どう登るか」を自分で考える力も同時に鍛えられるスポーツです。
ルート選びや手足の使い方を自分で考えることで、問題解決力や集中力も高まります。
さらに、成功体験が積み重なることで自己肯定感が自然と育つのも大きな魅力です。
第3位:殺陣(たて)〜サムライ魂、ここにあり〜

「殺陣(たて)」は、時代劇で見かける刀を使った立ち回りの動きを学べる習い事です。
集中力・礼儀・身体の使い方が一度に学べるということで、実はかなり実用的です。
何より「かっこいい!」という理由で、男の子にも女の子にも人気なんですよ。
| 対象年齢 | 料金目安 |
|---|---|
| 小学生〜 | 月8,000円前後 |
殺陣を習うメリット
殺陣の大きな魅力は、礼儀や姿勢を重視しながら身体を動かせる点にあります。
所作を美しく見せることが求められるので、姿勢や動きが自然と洗練されていくんです。
また、集中して一つの型を覚えていく過程で、忍耐力や集中力も鍛えられます。
第4位:和太鼓(伝統とリズム感)

バチを使って大きな音を出す「和太鼓」は、音楽というよりスポーツに近い感覚です。
リズム感や集中力が自然と育つのがポイントで、発表会での迫力は親も感動ものです。
| 対象年齢 | 料金目安 |
|---|---|
| 4歳〜 | 月5,000〜8,000円 |
和太鼓を習うメリット
和太鼓は、音楽的なリズム感と全身運動が同時にできる習い事です。
大きな音を出すことで、ストレスの発散や自己表現にもつながります。
演奏を通じてグループでの協調性も求められるため、チームワークや一体感を学ぶ場としても優秀です。
第5位:マジック・手品(表現力×観察力)

マジック(手品)は、人を驚かせる楽しさと、手先の器用さ・集中力・表現力が育つ習い事です。
「自分で仕掛けを作って、人を楽しませる経験」は、自己肯定感アップにもつながります。
| 対象年齢 | 料金目安 |
|---|---|
| 6歳〜 | 月5,000〜7,000円 |
マジックを習うメリット
マジックを習うことで、手先の器用さや観察力が鍛えられます。
トリックを覚えるだけでなく、「どう見せたら驚いてもらえるか」を考える力も育つため、表現力や想像力も伸びます。
さらに、成功したときの観客のリアクションが嬉しくて、自信や達成感につながるという声も多いですよ。
第6位:演劇(自己表現のすべてが詰まってる)

演劇は、表現力・共感力・コミュニケーション能力を育ててくれる習い事です。
「人前で話すのが苦手」という子にこそ、おすすめです。
チームワークや発表の達成感も大きな魅力です。
| 対象年齢 | 料金目安 |
|---|---|
| 幼児〜中高生 | 月6,000〜12,000円 |
演劇を習うメリット
演劇の最大のメリットは、「なりきる」ことで感情を表現する力が育つことです。
役になりきることで、他者の気持ちを想像する力=共感力が身につきます。
また、発表の場があることで、人前で話す練習にもなり、将来的なプレゼン力や面接力にもつながります。
第7位:DJ(音楽好きキッズに人気爆発)

音楽をつなぎ、空間を作る「DJ」は、音楽好きな子どもに大人気の新ジャンルです。
機材の扱い方を学びながら、リズム感や音感、センスを養うことができます。
| 対象年齢 | 料金目安 |
|---|---|
| 小学生〜 | 月8,000円前後 |
DJを習うメリット
DJの習い事では、音楽の構成を考える力や、曲と曲のつなぎを工夫する創造力が求められます。
流行りの音楽を分析したり、自分なりの選曲を考えることで、感性やセンスも磨かれます。
さらに、イベントや発表の場で披露する機会があると、プレゼン力や度胸も自然と身につきますよ。
第8位:パルクール(アクロバティックな都市型スポーツ)

障害物を乗り越える「パルクール」は、まるでアクション映画のようなスポーツです。
見た目以上に安全性が考えられていて、怪我をしないための身体の使い方が身につきます。
| 対象年齢 | 料金目安 |
|---|---|
| 小学生〜 | 1回3,000円〜/月10,000円前後 |
パルクールを習うメリット
パルクールでは、全身を使ったバランス感覚と柔軟な身体操作が鍛えられます。
単なる運動ではなく、「どうすれば安全に越えられるか」を考えながら動くことで、判断力や空間認識力も高まります。
派手に見えて実はとても実用的な、現代的な身体教育ともいえる習い事です。
第9位:モルック(北欧発の新感覚スポーツ)

木製のピンを使った北欧発のスポーツ「モルック」。
家族で一緒に楽しめることも人気の理由です。
ルールがシンプルなので、誰でもすぐに始められます。
| 対象年齢 | 料金目安 |
|---|---|
| 5歳〜 | 体験1,000円〜 |
モルックを習うメリット
モルックは体力だけでなく、戦略的な思考も必要とするスポーツです。
スコアを計算したり、相手の動きを読みながらピンを倒すので、思考力や集中力が自然と鍛えられます。
また、子どもと大人が一緒に対等に楽しめるため、世代を越えた交流のきっかけにもなります。
第10位:ジオラマ(創作×集中力)

小さな世界を作り出す「ジオラマ」は、創作意欲・空間認識・集中力を高めるアート系習い事です。
完成した作品をSNSでシェアする楽しさもあり、達成感を味わえるのが魅力です。
| 対象年齢 | 料金目安 |
|---|---|
| 小3〜 | 月8,000〜10,000円 |
ジオラマを習うメリット
ジオラマ作りは、細かい作業に集中する力や、空間を立体的に捉える力が鍛えられます。
「どんな配置にしよう?」「ここはどう再現しよう?」と考える過程で、観察力や計画力も育ちます。
作品が完成したときの達成感も大きく、成功体験を積みたいお子さんにぴったりです。
昭和時代と令和時代の習い事はなぜこんなにも違うのか
- 昭和は「基礎力・学力重視」が当たり前だった
- 令和は「個性・体験重視」へとシフトしている
- 社会の価値観が大きく変わった
- テクノロジーとSNSが新しい習い事を生み出した
昭和は「基礎力・学力重視」が当たり前だった
昭和時代の習い事といえば、「そろばん・習字・ピアノ」などの定番系が中心でした。
これらはすべて、学力や集中力を高めるための“勉強の補助”という位置づけでした。
習い事を選ぶときの基準は、「勉強に役立つかどうか」や「受験で有利になるか」が最優先だったんです。
また、当時の子育ては「しつけ・礼儀・努力」といった価値観が強くて、親の意志で習わせるのが普通でした。
子どもが「やりたい」と言う前に、親が「やらせたい」で決まっていたんですね。
令和は「個性・体験重視」へとシフトしている
令和の時代になると、習い事の種類が一気に広がりました。
プログラミング・ボルダリング・演劇・パルクールなど、昔では考えられなかった分野が人気になっています。
その背景にあるのは、「これからの時代に必要な力」が変わってきたことです。
AI時代の今、暗記力よりも創造力・柔軟性・表現力の方が求められるようになってきました。
そのため、子どもたちも「自分の好きなこと」「自分にしかできないこと」を大切にするようになってきたんです。
また、習い事を選ぶときも、子どもの「やってみたい」が出発点になっています。
これは、親の子育て観の変化でもあります。
親が「やらせる」から、「応援する」へとスタンスが変わってきているんですね。
社会の価値観が大きく変わった
昭和の頃は、「いい学校に入って、いい会社に入る」というルートが成功の定番でした。
でも今は、SNSやYouTube、フリーランスといった“新しい働き方”が当たり前になっています。
「自分らしく生きる」「好きなことで生きていく」という考え方が広まっているからです。
こうした価値観の変化が、習い事にも大きな影響を与えています。
個性を育てることが、そのまま将来の仕事や生き方に直結するようになってきたんですね。
そのため、「他の子と同じように」よりも、「その子らしく」習い事を選ぶ時代になっているんです。
テクノロジーとSNSが新しい習い事を生み出した
もうひとつの大きな変化は、テクノロジーの発達とSNSの普及です。
今の子どもたちは、小さいうちからタブレットやスマホに触れ、自分でコンテンツを作って発信することも珍しくありません。
この影響で、発信力やデジタルスキル、表現力を重視した習い事が増えてきました。
たとえば、マイクラでプログラミングを学ぶ、DJで音楽センスを磨くといった習い事もその一例です。
習い事=誰かに習うだけでなく、「自分から発信する場」にもなってきているんです。
時代に合わせて、習い事もどんどん進化しているというわけですね。
まとめ
昭和の時代とはまったく違う、多様で自由な習い事の世界に驚いた方も多いのではないでしょうか。
でもどんな時代でも、子どもの習い事に大切なのは「楽しさ」と「本人のやる気」。
どれだけ未来に役立ちそうでも、本人がワクワクしないと続きません。
逆に、ちょっと変わった習い事でも、楽しんで続けられればそれが一番の才能につながることだってあります。
「こんな習い事、うちの子も好きかも?」と少しでも感じたら、ぜひ体験からでも試してみてくださいね。
子ども時代の“楽しい記憶”が、その子の未来の力になるかもしれません。

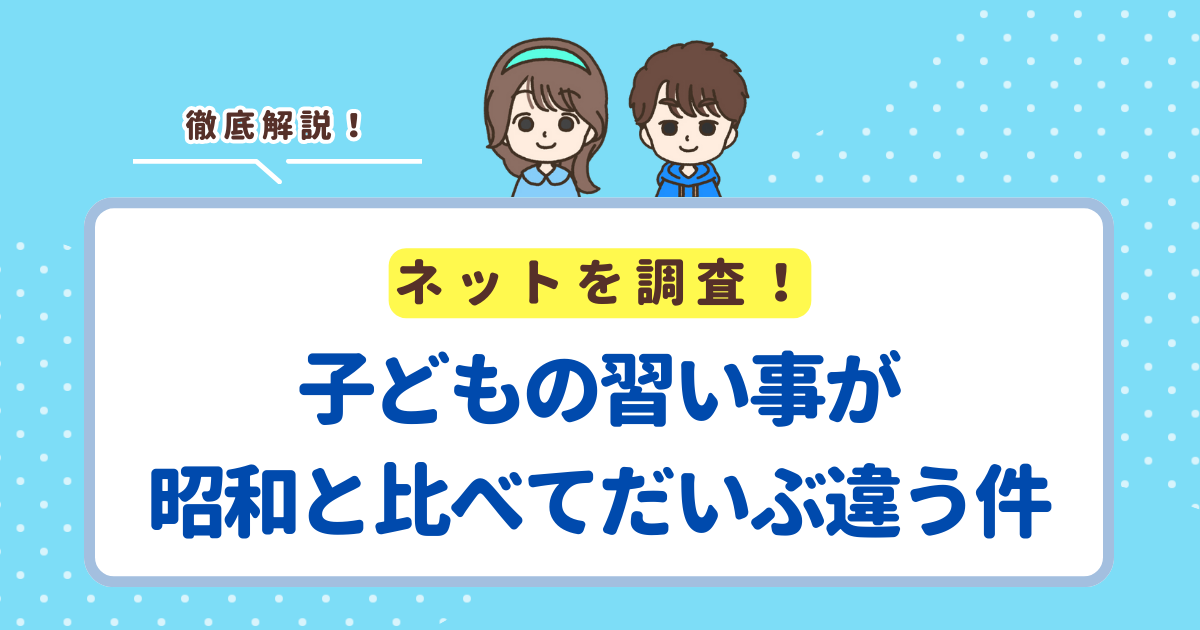

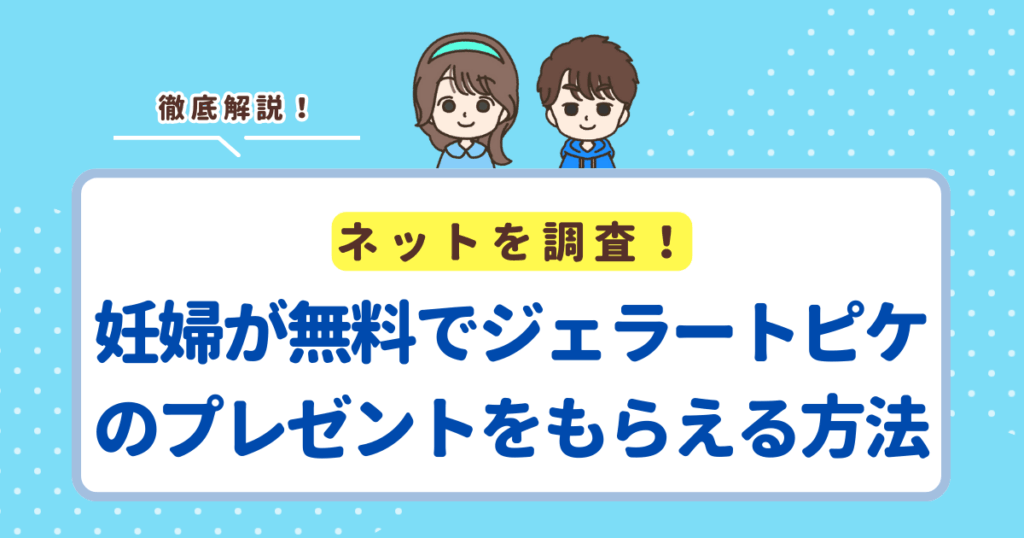
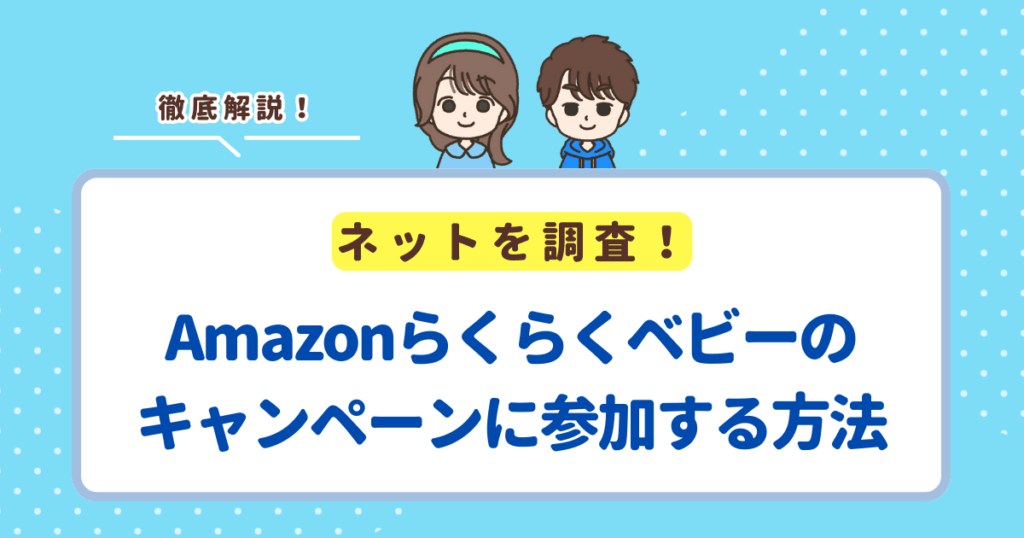
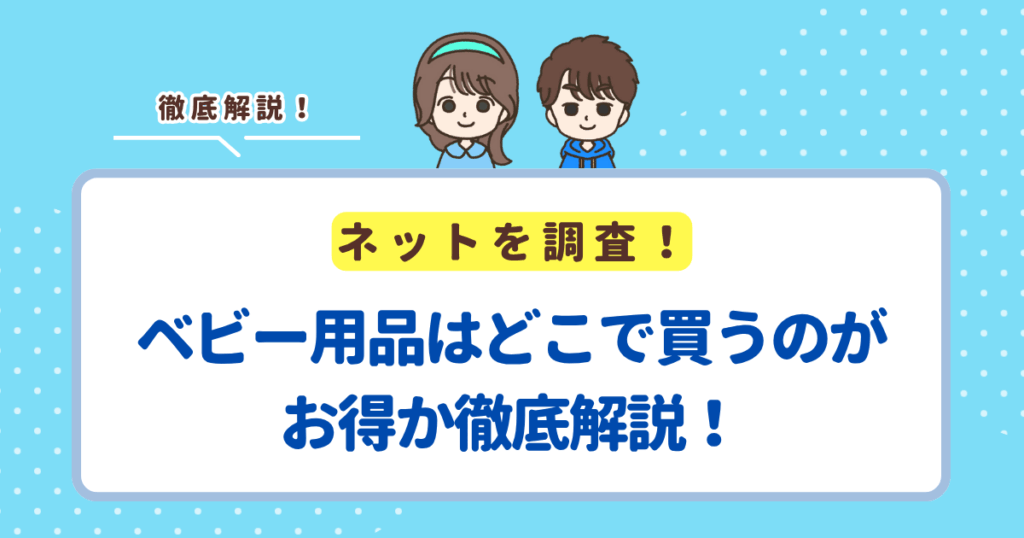

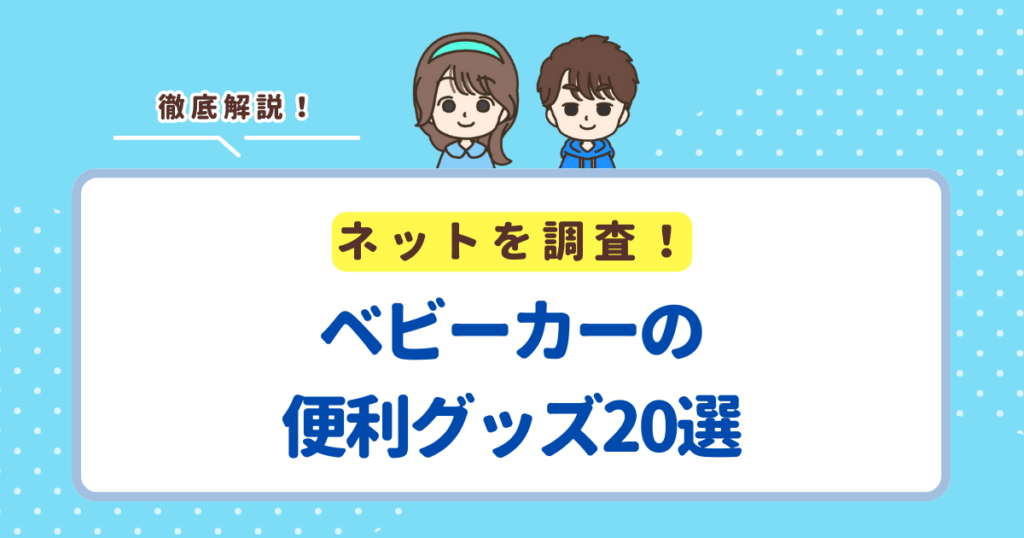
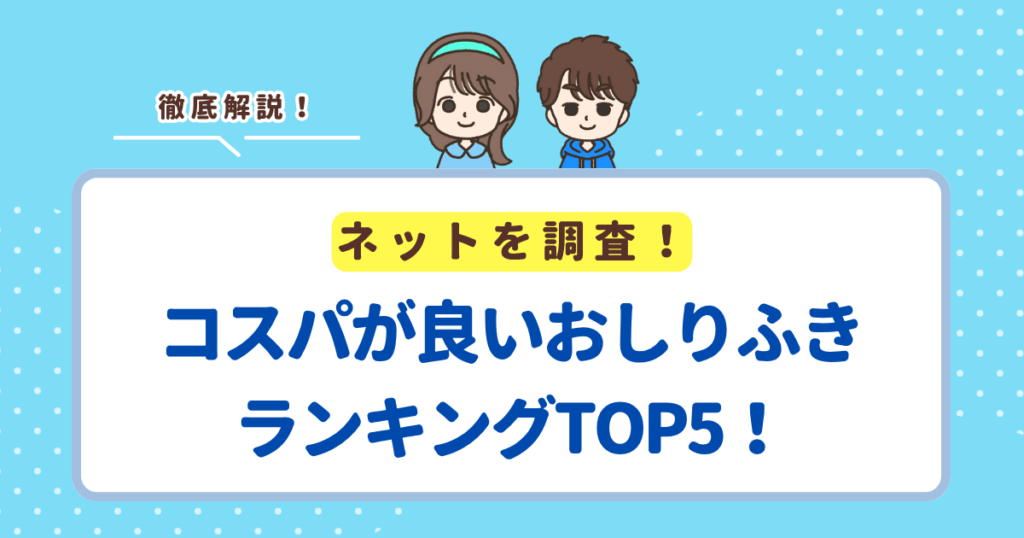
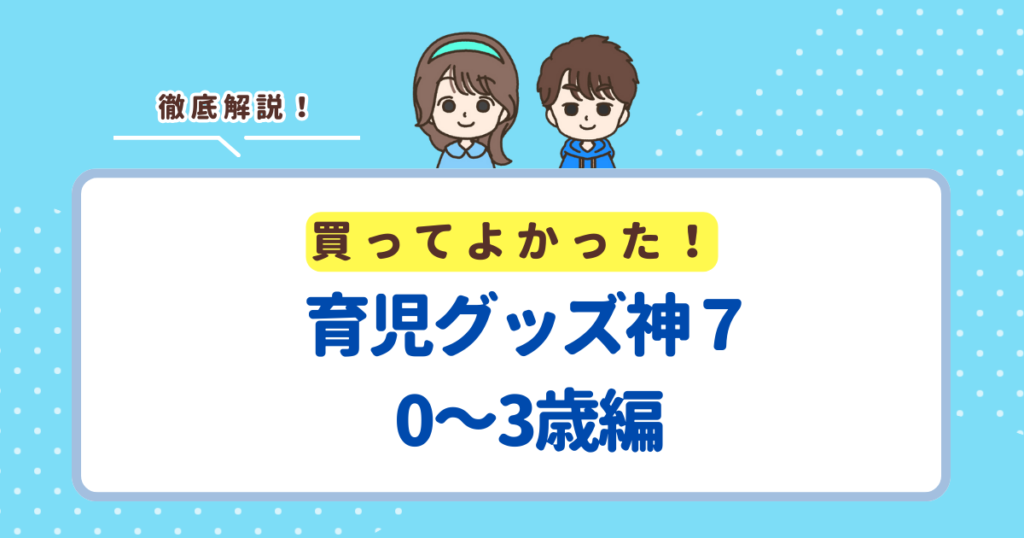
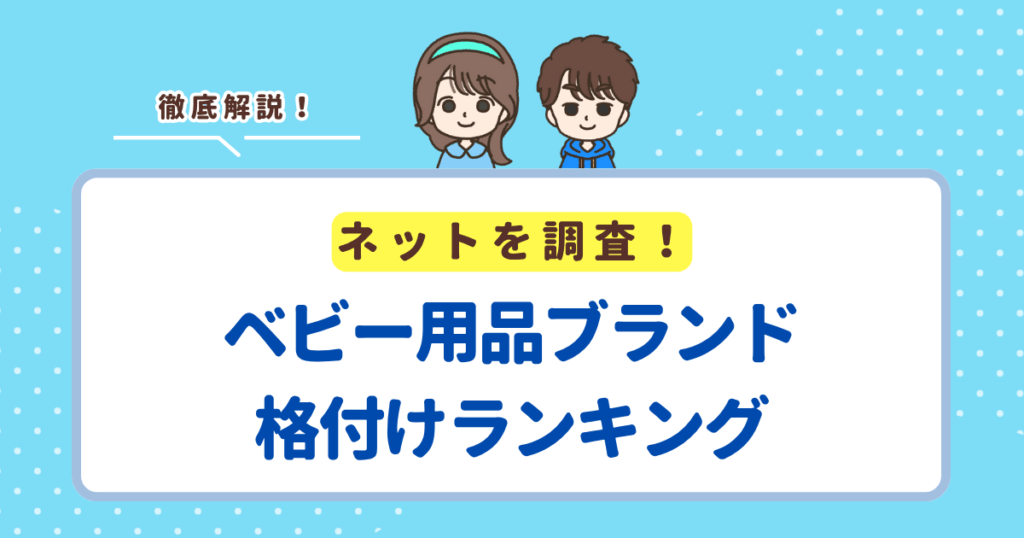
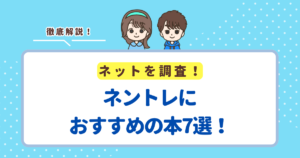

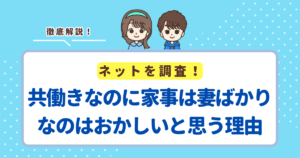
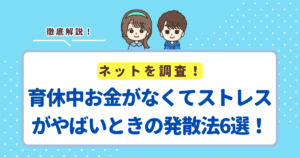
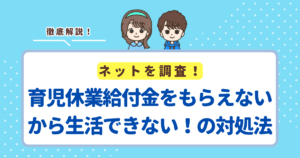
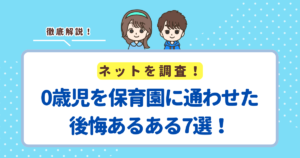
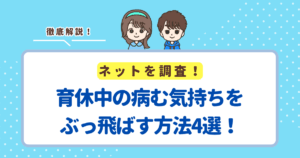
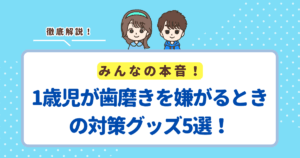
コメント